オスカー・ワイルドの代表作『ドリアン・グレイの肖像』は、美と魂、欲望と罪、そして救済と破滅をめぐる寓話として知られる。本稿では、作品を読んだ直後に私自身が抱いた断片的な直感――「魂、老い、美、上流貧困の魂」「堕落、罪の意識、許し、物質と精神」など――を出発点として、ワイルドの思想を探る試みを行う。
初期直感:美と魂の二重性
『ドリアン・グレイの肖像』を読んでまず直感したのは、美の力が人を救うと同時に堕落させるという矛盾である。
美は憧憬の対象であり、人の心を高める。
しかし美は同時に欲望を呼び覚まし、人を破滅に導く。
人は美に弱く、抗うことができない。
この直感は、ワイルドが唯美主義の旗手でありながら、美の破壊的側面をも敏感に感じ取っていたことに通じる。
ワイルドにおける美の立場
ワイルドは美を単に礼賛したのではない。彼にとって美は「愛すべきもの」であると同時に「恐るべきもの」でもあった。
賞賛:美は最高の価値であり、倫理や実用を超える。
畏怖:美の力は人を堕落させる毒を秘めている。
皮肉:上流社会の虚飾を見抜き、冷笑する。
依存:自らも美と享楽の世界に深く惹かれていた。
したがって『ドリアン・グレイの肖像』は、美を一方的に肯定も否定もせず、愛憎と矛盾を込めて描いた作品である。
美が堕落を導く理由
美はなぜ人を堕落させるのか。考えられるのは次の三点である。
1. 欲望の刺激:美しいものを前にすると、人は「所有」「独占」を欲する。
2. 永遠性への執着:美の刹那性に抗い、不自然な手段で保存しようとする。
3. 倫理の相対化:美醜の基準が善悪を上書きしてしまう。
ワイルドが描いたのは、美と魂の均衡が崩れたときに起こる堕落の連鎖であった。
ヴィクトリア朝という背景
この物語はヴィクトリア朝という時代性を抜きにしては語れない。
社会は厳格な道徳を強調しつつ、裏では享楽と二重基準が蔓延していた。
帝国の繁栄と植民地支配の裏で、格差と精神的空虚が広がっていた。
表面的な禁欲と内面的な退廃――この矛盾こそがワイルドの標的であった。
『ドリアン・グレイの肖像』は、まさにこの二重性を鏡のように映し出す文学的実験である。
三人の登場人物=ワイルドの分身
本作の三人の主要人物は、それぞれワイルド自身の一部を体現している。
ドリアン・グレイ:永遠の美と享楽への憧れ。
ヘンリー・ウォットン卿:皮肉と機知をもって社会を冷笑する知識人。
バジル・ホールワード:芸術を魂の表現と信じる良心。
ワイルドは現実にはヘンリー卿的に振る舞い、ドリアンに憧れつつも、最後にはバジル的な「魂の重さ」に押し潰されていった。
「結局ワイルドはバジルだった」という視点
しばしば「ワイルド=ヘンリー卿」と言われるが、実際には 「ワイルドは最後にバジルでしかありえなかった」 とも考えられる。
ドリアンのように美に支配されることは夢にすぎない。
ヘンリー卿のように冷笑だけで生き延びることもできなかった。
最後に残ったのは、魂を抱え込んで苦悩し、傷つき、破滅する芸術家=バジルの道であった。
この見方は、ワイルドの人間的矛盾を最も端的に表すものかもしれない。
美の羅列に宿るワイルドの暴力性
さらに、作中中盤で描かれる「美の羅列」に注目したい。
ドリアンが宝石、衣装、宗教儀礼、工芸品、音楽などあらゆる美を次々と渇望する章である。
表面的には「ドリアンの享楽と堕落の象徴」と読まれることが多い。
しかし私には、この章は単なる堕落描写ではなく、ワイルド自身の「美に対する焦がれと暴力性」の爆発に見えた。
焦がれ:現実世界で手に入れられない美を、言葉として所有する欲望。
暴力性:読者を置き去りにしてでも美を圧倒的に提示する強さ。
作家の特有の力:理解されなくても構わない、圧倒して見せる、という文体の強引さ。
この章は、ドリアンの堕落の描写であると同時に、ワイルド自身の魂と審美的欲望の告白でもある。
つまり、美の羅列は三重の意味を持つ――
1. ドリアンの堕落の進行
2. 読者を圧倒する美体験
3. 作家ワイルド自身の「美への執着」の表出
結論
ワイルドにとって美は、愛し、恐れ、皮肉り、依存し、そして破滅をもたらす存在であった。
『ドリアン・グレイの肖像』は、その矛盾を三人の登場人物に分割して描いた寓話であり、最終的にワイルド自身が選び取ったのは「芸術と魂に殉じるバジルの道」であった。
さらに、中盤の美の羅列を通して、ワイルドは自身の焦がれと暴力性を作品に注ぎ込んでいる。
美は堕落をもたらすが、同時に読者を圧倒し、作家自身の魂の深みを見せる力を持っている。
こうしてワイルドは、永遠の美への憧憬と現実の苦悩、享楽への渇望と魂の重さという二重性を、『ドリアン・グレイの肖像』という一冊に凝縮したのである。
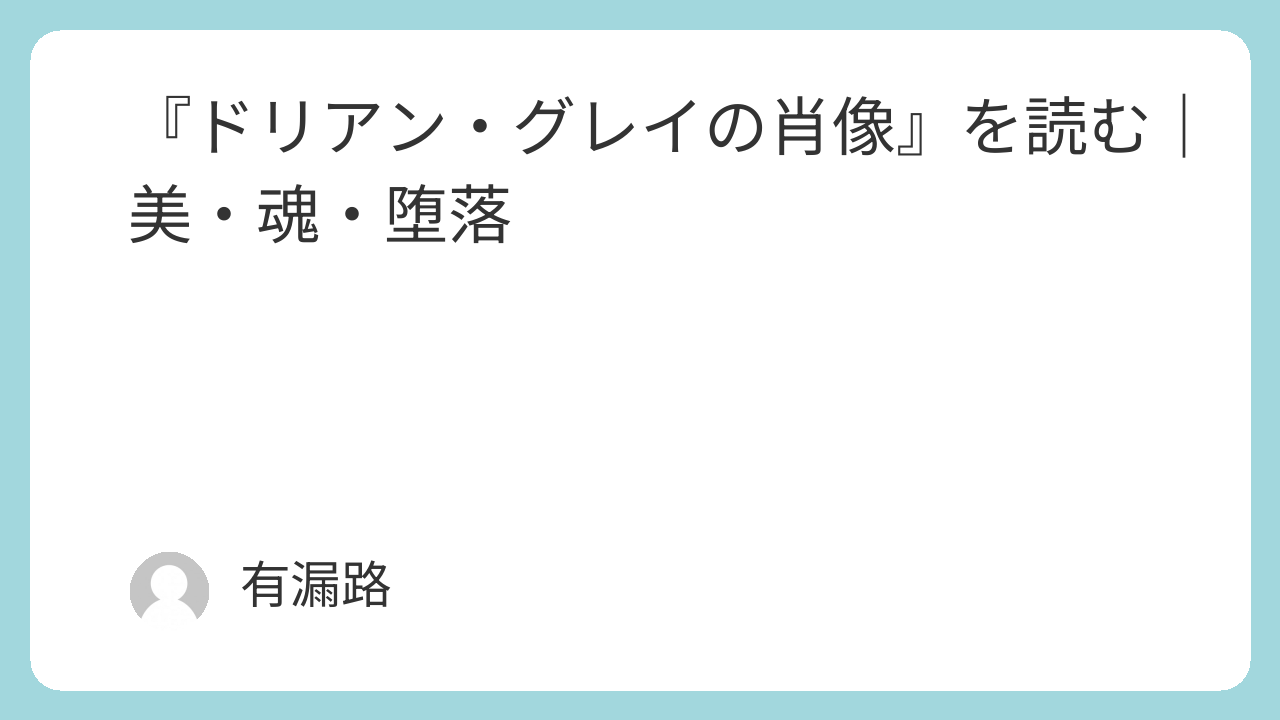
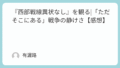
コメント