何においてもセンスが求められ、センスの良し悪しで人がカテゴライズされがちな今、そもそも「センスとは何か」を少しでも知りたくて、千葉雅也さんの『センスの哲学』を手に取りました。
「意味」に縛られる鑑賞体験
最近、漫画や映画を「即物的に」見ることが少なくなってきたように思う。
登場人物の行動の「意味」、物語に込められた「メッセージ性」、そういったものを読み解こうとする姿勢が当たり前になっている。
YouTubeやTwitterを覗けば、ファンによる深い考察がずらりと並んでいて、その深い洞察力に感心する。羨ましくなる。
こんなふうに考えられたら、もっと色んな作品が楽しく感じられるのだろうなと思ってしまう。
反面、少し疲れるときもある。
「即物的」な鑑賞体験への回帰
この本の中で著者は「即物的に」見ること、ものごとをただそのまま受け取ることの価値を多様な言葉や視点から語っていた。
意味の前の段階、例えば、小説の言葉に含まれた意味をくまなく拾い上げるよりも、文体の色香に酔いしれたり、絵画から作者の意図を読み解くよりも、機械的に0と1の感覚で眺める、といったような、この本で言う「リズム」的な受け取り方――瞬間的で刹那的な見方に立ち戻ってみてもいいのではないだろうか。
「意味」ではなく「リズム」で見る
「リズム」的な見方とは、「意味」になる前の、言葉になる前の、名前もない思いにもっと目を向けることだと著者は語る。
考察することで孤独になる瞬間
例えば、考察という行為は、そこに自分の個性を映し出すものだと思う。
それ自体は面白くて魅力的だが、ときに自分の無自覚な身体性や感受性が他人の解釈とぶつかって、解釈違いという言葉が生まれる。
まるで、作品を自分なりに解釈することが、正誤のあるテストのように感じられてしまう瞬間がある。
流れに身を委ねた体験へ
けれど私は、必ずしもものごとを再現しようとしなくていいのでは、と思う。
ただ、その場面に身を委ねる、流れるままに眺めていく。
考察し分析した結果ではなく、そうして何気なく心に残っているものこそ、実は一番強く、その作品に触れた証なのかもしれない。
意味の手前に存在している「センス」
そもそも、自分自身をひとつの芸術作品と見なすなら、何かを見るとき、読むとき、行動するとき、いつも「意味」を求めがちになる。
それは社会で円滑に穏やかに生きていく上で必要な処世術だと分かっている。社会で求められる重要なことだったりする。
あるいは何か意味づけることで自分を安心させたいという逃げか癖なのかもしれない。
ただ心の赴くままに、ふらふらと描いたり、読んだり、動いたりする中に、自分という存在の「かたち」がにじみ出てくるのではないか。
アイデンティティとは、案外、意味を追いすぎずにいるときの方が、姿を見せてくれるのかもしれない。
それがきっと「センス」というものではないか、と思えてくる。


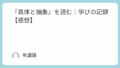
コメント