具体と抽象を同じ粒度で捉えていた
「具体と抽象を行き来することが大事」だと読んで気付いた。
これまで自分は、具体と抽象を同じ粒度で扱っていた。
例えば歴史を学ぶとき、用語を覚えること、全体の構造を理解することを、同じレベルで「一度に覚えよう」としていた。
結果として、取捨選択ができず、知識が頭にうまく定着しないことが多かった。
読書の方法も同じで、最初から細部まで精読し、頭に叩き込もうとしていた。
しかし、そのやり方は負荷が大きく、むしろ全体像を見失う原因になっていたように思う。
読み方を分けるという発想
本を読む際には、一回目からすべてを覚えようとするのではなく、段階を踏んだ方が良い。
例えば世界史ジャンルの本を読むとき、一回目は全体の構造を把握することに集中し、二回目以降に細部の内容を覚えていく。
さらに読み方にテーマを設定することで、理解は一層深まるだろう。
例えば今回は「人物の動き」に注目して読む、次回は「権力の移り変わり」に焦点を当てる、といったように、視点を変えて繰り返すことで、それぞれの要素が立体的に結びつく。
単なる暗記ではなく、知識のネットワークを築く作業になる。
著者が示す抽象化の多様な顔
本書の中で著者は「抽象化」という言葉を、多様な表現で説明していた。
法則パターンを見つけること、構造把握、関係性、共通点と相違点を見つけること、指針、座標軸、相対性、幹、デフォルメ、目的によって変わる抽出。
これらの言葉の詳しい意味はぜひ本を読んでほしいが、これまで自分にとって「抽象化」は曖昧で掴みどころのない概念だった。
しかし、こうして言い換えを重ねられることで、抽象化のイメージが少しずつ輪郭を持ち始めた。
抽象化とは、複数の具体例を前提にして、その中に潜む共通点や構造を見抜く営みだと言える。
疑似体験と量の意味
特に共通点と相違点を見つけて抽象化していくには「量」が欠かせない。
映画を観る、小説を読む、歴史書に触れる――そうした多様な経験の積み重ねは、たとえ直接の体験ではなくとも、疑似体験として自分の中に蓄積されていく。
疑似体験が増えると、共通点や相似点を発見しやすくなる。
最近の個人的な話で例えると、世界史の概説書を読んだ後にキリスト教史の本を読むと、知っている単語がいくつも出てきて理解が進んだ。
さらに吸血鬼伝承の本を手に取れば、宗教や社会不安との関連が見えてきた。
これらはまさに、複数の具体例を通じて抽象的な構造を掴むプロセスである。
今後の読み方に向けて
抽象化とは、決して難解な操作ではない。
複数の事例を知り、その中から共通する構造やパターンを見抜くこと。知識を横につなぎ合わせること。
そのためには、とにかく量をこなすことが前提になる。
本を一度で「完全に理解しよう」とするのではなく、複数回に分けて「座標軸を少しずつ描いていく」こと。その積み重ねが、抽象的な理解を支える基盤となるだろう。
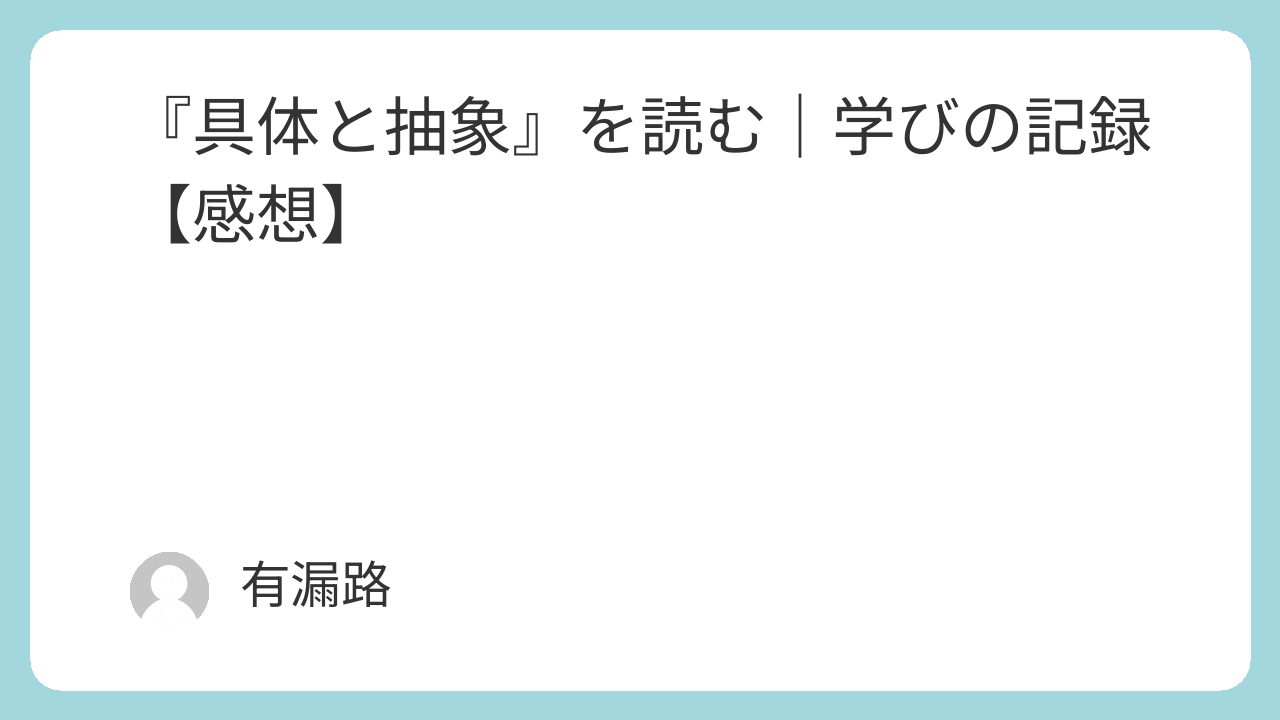

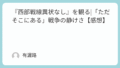
コメント